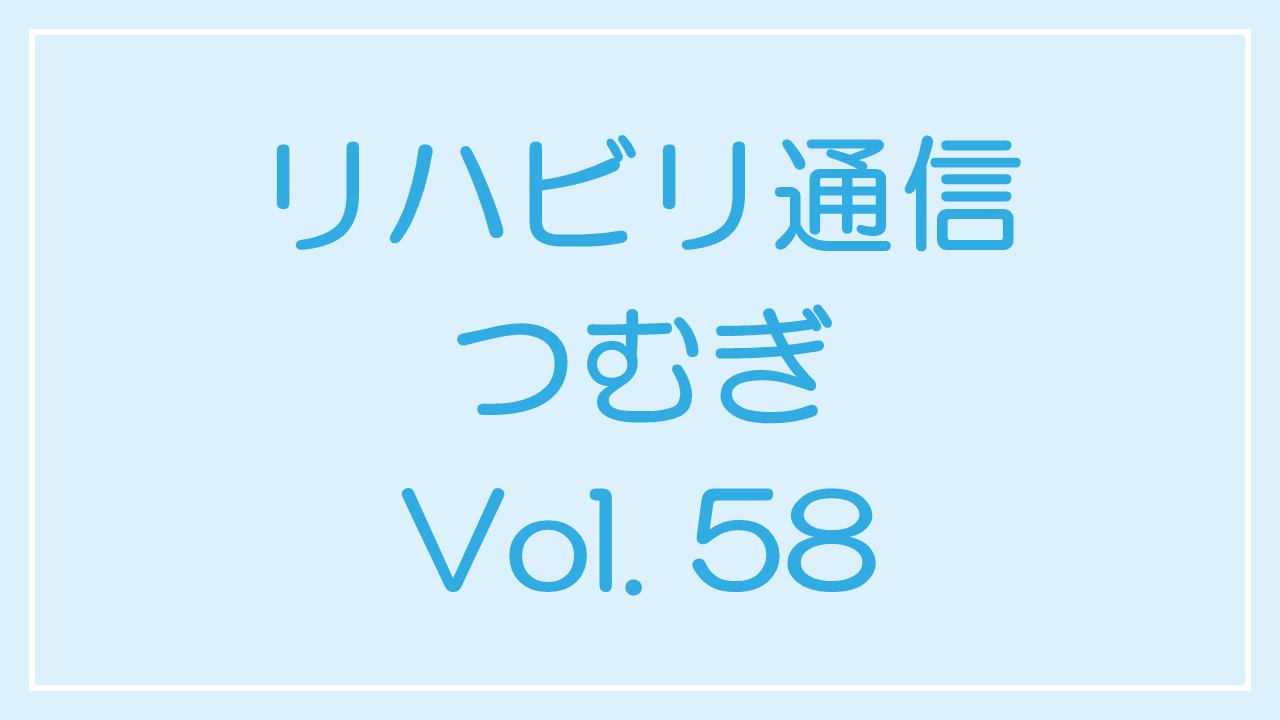こんにちは。
言語聴覚士の星野と申します。
今回は摂食嚥下障害に対する治療の一例をご紹介させていただきます。
摂食嚥下障害とは、様々な原因により食べたり飲んだりする過程のどこかに問題が生じている状態をいいます。症状としては、食べたり飲んだりする際にむせ込む・口の中に食物が残ってしまう・口角から食物や水分が垂れる・痰が絡むなど様々です。これらの症状が誤嚥性肺炎・窒息・低栄養などの原因となる事があります。
現在の高齢化社会に伴い、脳血管疾患や神経変性疾患などによる嚥下障害や誤嚥性肺炎が増加しています。当院でも多くの患者さんの摂食嚥下障害に対し言語聴覚士によるリハビリを実施しています。
摂食嚥下障害に対する訓練法は多くありますが、近年では言語聴覚士が行う嚥下訓練に加え神経筋電気刺激機器を併用する事で相乗効果が得られるというエビデンスが集積されています。また神経筋電気刺激機器は2000年代はじめに脳梗塞後の嚥下障害を改善させるという最初の報告がされて以来、多くの研究報告がされており、現在では病院やクリニックで標準的な治療方法として導入されています。当院では日本摂食嚥下リハビリテーション学会をはじめとする多くの学会でその治療効果が期待されているジェントルスティム(株式会社フードケア)を導入し患者さんの摂食嚥下リハビリに活用しています。


電極をのどに貼り付けて使用します。 ジェントルスティム(株)フードケア
ジェントルスティムの電気刺激は干渉波という特殊な周波数の電流を作る為、痛みも少なく、のどの奥の神経まで作用します。嚥下障害の方に起こりやすい飲み込みの反射の遅れを軽減し、誤嚥物を喀出する為に必要な咳反射が出やすくなるなどの効果があると言われています。のどに必要な感覚の鋭敏さを高め、安全に経口摂取が行えるようジェントルスティムを積極的に使用しています。
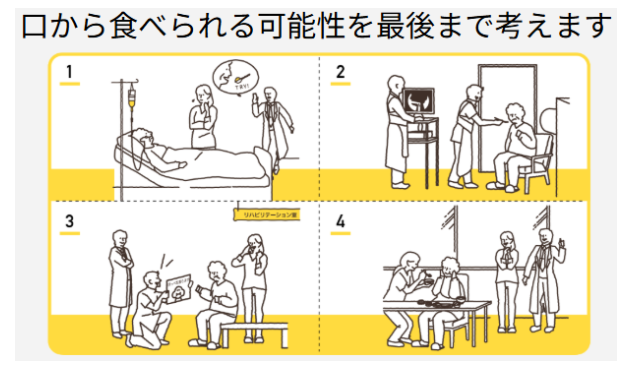
当院の診療方針の一つに「口から食べられる可能性を最後まで考えます」と掲げています。これからもチームで患者様の「食べる」に寄り添えるよう、努めてまいります。

今回の執筆者:言語聴覚士 星野 貴彦(ほしの たかひこ)
趣味:サーフィン
昨年度、千葉県から平成横浜病院へ入職させていただきました。今年度で言語聴覚士として10年目を迎えました。出身地でもある横浜で皆様に貢献できるように励んでまいります。